サンライズの
現場ブログBLOG
ブロック塀解体とは? (神奈川県横浜市解体ブログ)

東京、神奈川県の皆様こんにちは。
今年にはいって早くも2週間がたち、普通の日常に戻ってきました。ブログ担当です。
今回はブロック塀解体について解説していきます。
ご自宅のブロック塀をチェックしたり、実際に解体工事を依頼する際の参考にしてくださいね!

建物だけではなく、建物の周りにあるフェンスやブロック塀。
また、場合によって壊さなければならないブロック塀などいろいろありますよね。
みなさんの中には、「ブロック塀の解体工事にかかる費用の相場は?」「解体が必要なブロック塀のチェックポイントが知りたい」「解体を依頼するかもしれないのでブロック塀解体の手順を知っておきたい」などなど、疑問をお持ちの方もいると思います。
目次
ブロック塀の解体費用相場
まず気になるブロック塀の解体費用の相場をご紹介します。
ブロック塀の解体工事の費用は、一平米あたり5,000円~10,000円とされています。
業者ごとに異なるので、複数の業者から見積もりをとって比較することをおすすめします。
では、費用項目ごとに見ていきましょう。
人件費
ブロック塀の大きやさ状態にもよりますが、東京近郊の場合は1人の作業員につき1日あたり20,000円~25,000円ほどの費用がかかるとされています。
運送費
運送費は使われるトラックの大きさによって変わってきます。トラックの大きさは撤去されるブロック塀の多さに比例します。
トラックを手配するための費用は、1台あたり5,000円~10,000円ほどとなっています。
廃材処理費用
ブロック塀の解体・撤去にともなう廃材を処理する費用がかかります。
廃材の処理費用は廃材の量ではなく質によって決まり、場合によっては数万円以上かかることもあります。
解体が必要なブロック塀の特徴
では、解体が必要なブロック塀の特徴を見ていきましょう。
以下にご紹介する特徴が見られたら危険信号です。
高すぎる
ブロック塀の高さは上限が2.2mまでと法律で決められています。
この高さを超えるブロック塀は法律違反であり、倒壊の危険もあるので撤去が必要になります。
レンガ造・石造・鉄筋が入っていないコンクリート造のブロック塀は1.2m以下にするのが安全です。
厚さが不十分
建築基準法で定めるブロック塀の厚さは10cm以上ですが、全国建築コンクリートブロック工業会は12cm以上を推奨しています。
ブロック塀の強度は高さと厚さのバランスがとても大切です。
例えば、
- 厚さが15cmであれば高さは2.2m以下
- 厚さが10cmであれば高さは2m以下
という具合です。
ひび割れがある
経年劣化によってブロックにひびが入ることがあります。
ひび割れがあるブロックは危険なので注意しておきましょう。
傾きがある
ブロック塀が傾いているのは劣化している証拠です。
傾いたブロック塀は地震などの衝撃があると倒壊してしまう恐れがあります。
基礎の部分が傾いている場合は特に注意が必要です。ちょっとした衝撃で倒れてしまう危険性があります。
鉄筋が通っていない
ブロック塀の中に鉄筋が入ってない場合は倒壊の恐れがあるので注意してください。
素人が外見だけで判断することは難しいため、不安がある場合は業者に点検してもらいましょう。
コンクリートの基礎が無い
コンクリートの基礎工事がなされていないブロック塀は大変危険です。
建築基準法施行令で、基礎の地上部分は35cm以上・地下部分の深さは30cm以上と定められています。
地下部分は見た目では判断できないので業者に見てもらいましょう。
築30年以上が経過
コンクリート製のブロック塀の耐用年数は30年と言われています。
30年を経過したブロック塀は劣化してもろくなっている可能性があるので注意しましょう。
ブロック塀の解体工事の手順
ブロック塀の解体工事の流れについてご紹介します。
解体工事の大よその流れを知っておくと、実際に工事を依頼する際の参考になると思います。
近隣への挨拶
解体工事で騒音が出る可能性があるので、トラブル回避のため近隣の住民に事前に挨拶をしておきます。
マーキング・コンクリートカッター
次にマーキング入れとコンクリートカッター入れという作業を行ないます。
マーキングとは解体する箇所に印を付ける作業です。マーキングで付けた印に合わせてコンクリートカッターを入れて解体します。
解体作業
ブロック塀の解体作業を行ないます。手作業の場合と重機を使う場合があります。
廃材の処理
解体工事後はブロック塀は産業廃棄物として処理します。
産業廃棄物処理のルールが法律で定められていますので、きちんとルールを守る業者なのかどうかも業者を選ぶ時のポイントです。
小口の補修と清掃
ブロック塀の一部を残す場合はセメントを使って小口の補修をします。
解体工事後にはこまごまとしたゴミが生じているので、最後にしっかり清掃をします。
ブロック塀解体では補助金制度を利用できる!
ブロック塀の解体工事では補助金制度を利用できます。
解体工事を依頼する際には積極的に活用しましょう。
補助金適用の範囲
補助金が適用される範囲は、ブロック塀に関する調査費用・撤去費用・改修費用などです。
具体的には、ブロック塀の耐震性を診断するための調査やブロック塀を解体し新しく作る場合などが該当します。
補助金の額は自治体ごとに異なる
補助金で支給される金額は自治体ごとに異なるので注意しましょう。
一例をあげると、東京都の北区では通学路等に面するブロック塀の撤去費用として一平米あたり20,000円(上限50万円)が助成されます。
参考「東京都北区HP」
以上、ブロック塀の解体についてご紹介しました。
もろくなったブロック塀を放置することは大変危険だということがお分かりいただけたかと思います。補助金制度なども活用して速やかに撤去しましょう。
ブロック塀の解体など各種解体工事はサンライズにお任せください!
当社の最大の特長は、
- 近隣の方々や施設への手厚い対応にて近隣クレーム0件!
- 年間300件以上の豊富な実績
- 徹底した現場の安心安全管理
の三つです。
「クレームの無い解体工事」をモットーとする当社は、近隣の方々や施設への手厚い対応・徹底した現場の安心安全管理で、多くのお客様から厚い信頼をいただいています。
当社は、一般家屋・ビル・マンションなどの建物の解体や残置物の撤去から整地まで、全てをワンストップで行なう「解体工事」のプロフェッショナル集団なので、安心してお任せいただけます。
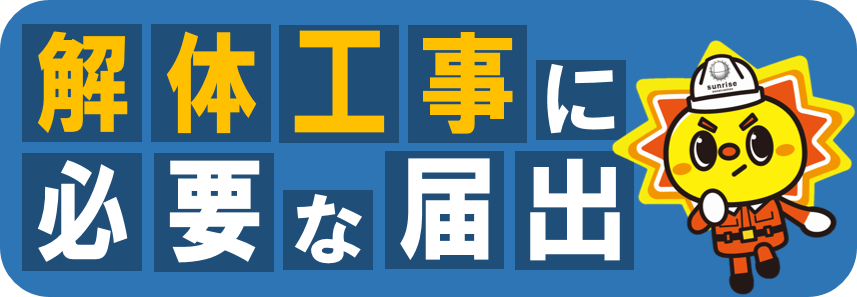
サンライズのスタッフSTAFF



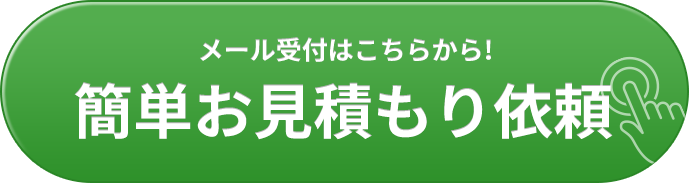








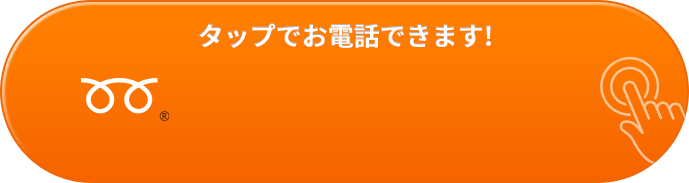
横浜地域密着の解体工事・家屋解体のプロにお任せください。
解体工事や家屋解体に関するお悩みごとは、些細な事でも私たちにお気軽にご相談ください!