サンライズの
現場ブログBLOG
建設リサイクル法とは?? (神奈川県横浜市解体ブログ)

横浜の皆様こんにちは。
横浜で解体業者をしております。株式会社サンライズのブログ担当です。
最近は花粉が酷くて大変ですね。横浜は今までの花粉より今年が一番多いみたいです。
しっかり花粉対策して乗り越えましょうね。
さて、今回は建設リサイクル法についてご紹介いたします。
横浜で家屋解体・解体工事をお考えの方でで守るべき「建設リサイクル法」についてご存知でしょうか?
「建設」と聞くと、新たに建物を建設する工事に対する法律かと思われるかもしれませんが、
ほとんどの家屋解体・解体工事は、この法律を守らずに行うことはできません!
更に、建設リサイクル法は解体業者だけでなく、工事の発注者である施主にも深くかかわる法律です。もしも施主のあなたが行うべき手続きを怠れば、罰則を受けることになるかもしれません。
建設リサイクル法とは
建設リサイクル法とは、平成12年5月31日に公布された法律で、
正式名称は「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」といいます。
建設リサイクル法は、わかりやすく言うならば建設資材のリサイクルを図るために作られた法律です。建築物の廃材が発生する、「建てる・直す・壊す工事」が対象となっており、家屋解体・解体工事はこの「壊す」工事に当ります。
建設リサイクル法の目的は、次の3つに分けられます。
1.建設資材リサイクルの義務付け
建設リサイクル法の目的のひとつが、建築物等に使用されている建設資材の分別、
もしくは建設資材廃棄物の再資源化を義務付けることです。
再資源化の対象となる資材は次のとおりです。

・コンクリート
・コンクリート、鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト
なお、伐採木、伐根材、梱包材等は建設資材に当てはまりませんので、
建設リサイクル法の対象ではありません。
解体業者から施主への報告の義務付け
家屋解体・解体工事の依頼を請けた解体業者は、建設リサイクル法の対象である資材の再資源化を行う際に、再資源化等の実施状況に関する記録を作成して保存し、再資源化が完了した際には、工事の発注者である施主にその旨を書面で報告する義務があります。
再資源化完了の報告を受け取った施主は、資材の再資源化が行われたことを認める際、
各都道府県知事に対し、再資源化の完了報告を受けたと申告します。
3.解体工事業登録と技術管理者選任の義務付け
建設リサイクル法により、平成13年5月31日より「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」のいずれの建設業許可も持たない解体業者は、元請け・下請けに関わらず、
各都道府県知事による解体工事業の登録なしには解体工事を行えないようになりました。
なお、登録には以下の要件を満たしている必要があります。
解体工事業登録の要件:不適格な業者ではないか?
不適格要件
①登録申請書や添付した書類に虚偽の記載があったり、重要な事実が記載されていなかった場合。
② 解体工事業者としての適性な営業が期待できない場合。
例えば、解体工事業の登録が削除されてから2年未満の場合。建設リサイクル法に違反し、罰金以上の刑罰を受けてから2年未満の場合。現在暴力団員であったり、暴力団員でなくなってから5年未満の場合などが当てはまります。
解体工事業登録の要件:適格な技術管理者を選任しているか?
技術管理者とは、解体工事現場において施工技術上の管理を行う管理者のことを言い、土木工学科等で専門知識を学び、一定以上の実務経験を持っている方や、解体工事現場での実務経験が7年以上の方が当てはまります。
建設リサイクル法では、解体業者に対して建設業許可の取得や解体工事業登録を義務付けることで、適切な工事・再資源化が行われるよう促しているのです。
建設リサイクル法を守った解体工事とは
建設リサイクル法で定められた解体工事のルールは、建設業許可または解体工事業の登録なしには解体工事をしてはいけない、というものだけではありません。
ここからは、建設リサイクル法による解体工事の決まりを見ていきましょう。
建設リサイクル法の対象となる解体工事
建築物の解体工事
建築物の解体工事の場合、特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルトなど)を用いた建築物の解体工事であることが前提であり、さらに、床面積の合計が80㎡以上の建築物が対象となります。
建築物の定義は、屋根・柱・壁のある建物と、門、塀、事務所、店舗、倉庫等の建物のことを言い、建築設備もこれに含まれます。
建築物以外の解体工事
土木工作物、木材の加工・取り付けによる工作物、コンクリートによる工作物、れんが、ブロック等による工作物や、機械器具の組み立て等による工作物の解体工事は、建築物の解体工事には当てはまりません。建築物以外の工作物の解体工事は、請負代金の額が500万円以上であれば、建設リサイクル法の対象となります。
建設リサイクル法を守った分別解体の流れ
さて、建設リサイクル法の対象となった解体工事の流れは次のとおりです。
①発注者が分別解体の計画表等の書類を都道県に届け出
②受注者が分別解体計画表にのっとり解体工事を施工
③受注者が対象資材の再資源化を実施
④元請業者が再資源化の完了を書面で発注者に報告
以上が建設リサイクル法に乗っ取った解体工事の流れです。
なお発注者である施主は、解体工事施工7日前までに届け出を提出しなければなりません。
廃材を分別しながら行う分別解体とは
解体工事というと、ミンチ解体のように建物をまるごと壊すものをイメージされるかもしれません。ミンチ解体とは、建築物に含まれるガラスや金属などの危険物も含め、建設資材を分別せずひとまとめにして壊してしまう工事のことをいいます。
現在ではミンチ解体は原則として禁止されており、廃棄物を種類・処分方法ごとに分別し、適切に処理することが建設リサイクル法において定められました。
分別解体ではまず解体予定の建築物を調査し、使用している建設資材を把握します。
それをもとに分別解体の計画を作成し、計画に則り工事をスタートします。家屋内部の内装材や屋根瓦、屋根ふき材は手作業で撤去していくことが多いです。
手作業での撤去作業が完了してから、重機による解体を行い、その際に発生した廃棄物も種類と処分方法によって分別を行い、工事終了後、適切な処理場にて処分を行います。
施主が守るべき建設リサイクル法
建設リサイクル法がどのようなものか、おおまかにご理解いただけましたでしょうか。
いざ自分が解体工事を依頼するその時、万が一にも建設リサイクル法を違反してしまうわないよう、解体工事の発注者である施主が行うべきことを把握しておきましょう。
施主が行うべき手続きって?
施主が提出するべき書類は、
- 届出表
- 分別解体等の計画表
- 付近見取り図
- 建築物全体がわかる写真
- 工程表
届出書は、各都道府県のホームページ等で確認できるほか、市役所などで受け取ることもできます。
分別解体計画表も、各都道府県のホームページからダウンロードすることができます。
計画表には主に、解体する建築物の事前調査の結果や、工事着手前に実施する措置の作業場所や搬出経路等の措置の内容、工程ごとの作業内容や硬い方法などを記入します。
計画表はほとんどレ点でチェックを入れるタイプのものですが、ご自身ではわからない箇所があった場合は、業者に確認しながら記入するようにしましょう。
届け出をしないと施主が罰せられる!?
施主による届け出の提出は、家屋解体・解体工事の施行開始7日前までが期限とされています。
万が一提出を忘れてしまったり、面倒だから…と提出を怠ると、
罰金20万円の罰則を受けることになってしまいます。気おつけましょう!
届け出の提出は解体工事を依頼した発注者、つまり施主に義務付けられています。
ですから、届け出の提出を行わなかった場合の責任は、発注者が負わなければなりません。
また、届け出を提出した場合においても、各都道府県から変更の命令があった場合、変更したものを提出しないでいると、さらに罰則が重くなりますので注意しましょう。
変更命令に従わなかった場合の罰則は、罰金30万円とされています。
なぜ提出義務は施主にあるのか
なぜ届け出の提出義務は施主にあるのかというと、分別解体・再資源化を行うためには、適切な費用で解体工事が行われることが前提とされているため、工事の発注者である施主自らが工事の内容を把握していて、了承した上で解体工事を発注していると示す必要があるためなのです。
概要だけでなく、写真や見取り図を施主に用意してもらうのにも、解体業者が勝手に提出してしまうのを防ぐためです。
うっかり出すのが遅れても、必ず提出しよう!
届け出の提出は、期限内を守り早めに提出することが一番です。
とはいえ、万が一施工7日前の期限を過ぎてしまっても、すぐに罰則が適用されてしまうわけではありません。
届け出の確認ができなかった場合、不備があり受理されなかった場合は、まず市役所から施主へその旨の通知がされます。
それでも反応がなければ是正勧告(行政指導)がなされ、それでもなお提出がなかった場合に、初めて罰則が適用されるのです。
提出をうっかり忘れてしまっていても、事情を説明し、すぐに提出することを約束すれば、
期限を過ぎていても待ってもらえることもあるかもしれません。
期限をもう過ぎてしまったからと諦めず、思い出したときにすぐ提出を心がけましょう!
株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、
ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、
東京、神奈川、近隣にお住まいの方々にも
信頼していただける丁寧な施工を提供いたします。
お見積り、ご相談は、フリーダイヤル: ( 0120-330-270 ) 、ライン からでもご相談できます。
いつでも、お気軽にお問合せ下さいませ♪
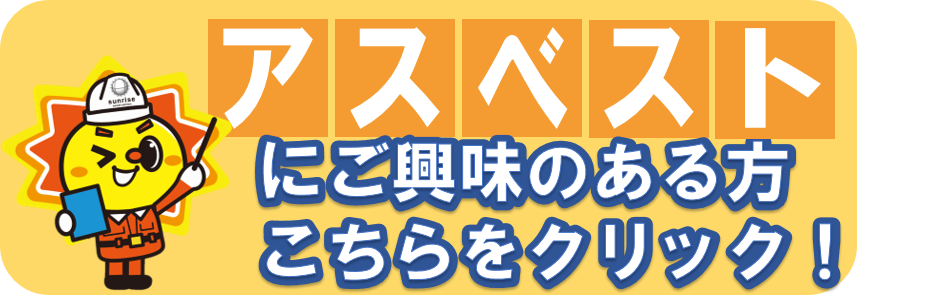
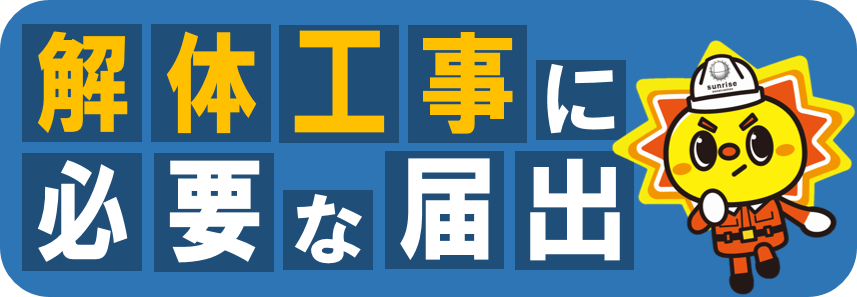
サンライズのスタッフSTAFF



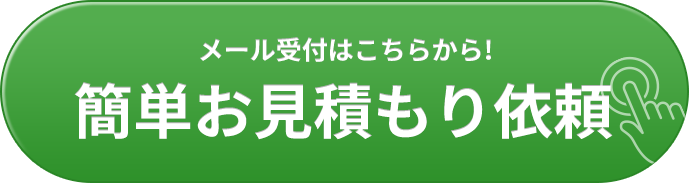








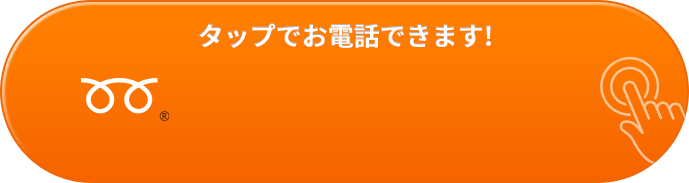
横浜地域密着の解体工事・家屋解体のプロにお任せください。
解体工事や家屋解体に関するお悩みごとは、些細な事でも私たちにお気軽にご相談ください!