サンライズの
現場ブログBLOG
アスベスト調査報告の義務化 (神奈川県横浜市解体ブログ)

横浜の皆様こんにちは。
横浜で解体業者をしております。株式会社サンライズのブログ担当です。
横浜で家屋解体・解体工事をお考えのかたも気おつけていただきたいアスベスト。
以前にもアスベストについてご紹介いたしましたが、今回も振り返りとして
アスベスト調査義務化について細かいところをご紹介いたします。
まず、アスベスト(石綿)とは繊維状ケイ酸塩鉱物の総称です。
アスベストにも種類がありますが法規制の対象は、
アクチノライト・アモサイト・アンソフィライト・クリソタイル・クロシドライト・トレモライトになります。
アスベストを吸い込むと肺がんや悪性中皮腫、石綿肺の健康被害が懸念されるため日本国内では現在、製造・輸入・新規使用が認められてません。
アスベストを含む建材(0.1重量%を超えるもの)は、労働安全衛生法により2006年9月から
製造・使用の一切を禁止されております。
横浜の新築物はアスベストを含む建材が使用されていませんが、2006年以前の建造物は使用されている可能性があります。このようなことから建物を解体・改修する前に、
アスベスト調査の義務化がされました。

義務化の開始期間はアスベストの事前調査は2020年より義務化されています。
更に2022年4月からは調査結果の『報告』を義務化されました。
調査結果を報告しなければ工事に関する補助金を申請できません。
事前調査は、原則としてすべての工事が対象となります。
工事規模や請負金額は関係ありません。
ただし、下記の条件を満たす工事は、施工業者が前もって労働基準監督署および自治体に、
事前調査結果を報告しなければなりません。
・解体部分の床面積が80㎡以上の家屋解体・解体工事
・請負金額が税込100万円以上の改修工事
・請負金額が税込100万円以上の一定の工作物の解体・改修工事
なお、電球交換などの軽作業、道路の補修作業など、
一部の作業についてはアスベスト調査が免除されます。
怠った場合の罰則
アスベスト事前調査の報告を怠ると、大気汚染防止法に基づき、30万円以下の罰金を科せられます。
また、アスベスト除去などの措置義務に違反すると3月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
気おつけておきたいところですね。
アスベスト調査・報告の流れ
①専門家に依頼
②書面および現地調査
③報告書作成
①専門家に依頼
アスベスト事前調査は、アスベストに関する知識と、建築物の調査に精通した専門家に依頼しなければなりません。具体的には、建築物アスベスト含有建材調査者、一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者、アスベスト作業主任者のうちアスベスト除去作業の経験を有する者などが対象です。
さらに、2023年10月からは、厚生労働省が実施するアスベスト調査の講習を修了していることが追加条件となります。
②書面および現地調査
設計図書などでの書面調査と、目視での現地調査は必須です。
場合によって、現地で採取したサンプルをアスベストの定性分析にかけることとなります。アスベストの定性分析とは、アスベストの含有率が0.1%を超えるかどうかを分析するものです。
設計図書などの書面だけでアスベストの有無を判断するのではなく、できるだけ建築物に赴いて部屋ごと・部位ごとの状況を確認しましょう。
③報告書作成
調査結果をもとに報告書を作成します。作成した報告書は、労働基準監督署や自治体に提出しましょう。解体工事開始の14日前までに提出しなければなりません。報告書は3年間の保存が義務づけられています。
また、実際に家屋解体・解体工事を進める際には、工事に関わるすべての建材についてアスベスト含有の有無を掲示しなければなりません。もしアスベストが一切無かったとしても、掲示しましょう。
掲示は、施主ではなく元請業者が担当いたします。
横浜の解体業者サンライズは石綿作業主任者資格を担当者が全員もっています。
家屋解体・解体工事をお考えの方でアスベストについて気になる方は
株式会社サンライズにお任せください!!
次回はアスベストの必要な届出についてご紹介いたします。
株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、
ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、
東京、神奈川、近隣にお住まいの方々にも
信頼していただける丁寧な施工を提供いたします。
お見積り、ご相談は、フリーダイヤル: ( 0120-330-270 ) 、ライン からでもご相談できます。
いつでも、お気軽にお問合せ下さいませ♪
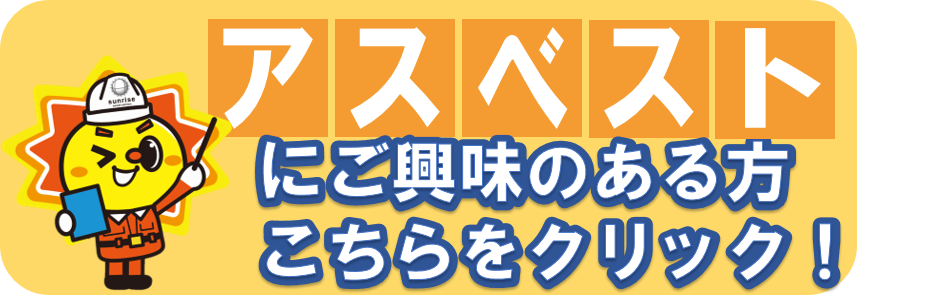
サンライズのスタッフSTAFF



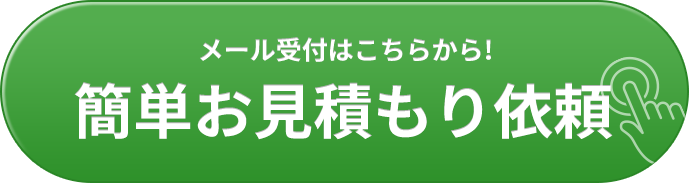








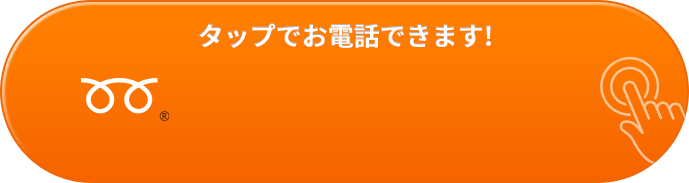
横浜地域密着の解体工事・家屋解体のプロにお任せください。
解体工事や家屋解体に関するお悩みごとは、些細な事でも私たちにお気軽にご相談ください!